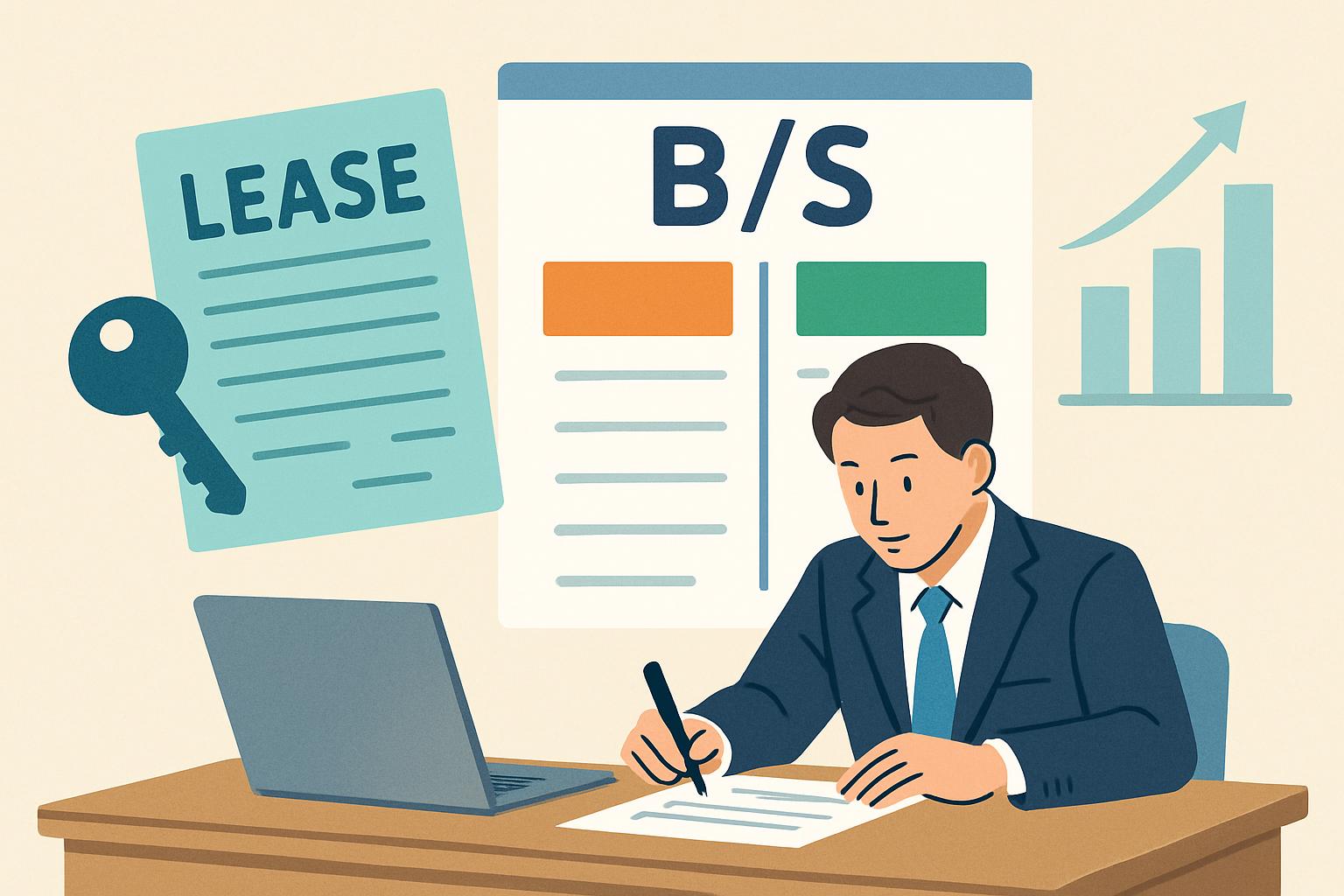新リース会計基準の適用が迫り、多くの企業で実務対応が求められています。この会計基準改正における最大のポイントは、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースを含め、原則として**すべてのリース契約を資産・負債として貸借対照表(B/S)に計上する**「使用権モデル」が導入される点です。本記事では、この新リース会計基準が「いつから」適用され、従来の会計処理から「何が」変わるのか、そして企業の財務諸表や経理実務に「どのような影響」があるのかを、図解や具体的な仕訳例を交えて基礎からわかりやすく解説します。IFRS第16号との関係性や中小企業向けの簡便的な取扱い、短期・少額リースの例外規定まで網羅し、新基準への移行で担当者が準備すべきことを明確に理解できます。
新リース会計基準とは そもそも何?
新リース会計基準とは、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表したリース取引に関する新しい会計処理のルール案です。これまで日本で適用されてきたリース会計基準が、国際的な会計基準(IFRS)との整合性を図るために大幅に見直されることになりました。最大の変更点は、これまで費用処理が可能だったオペレーティング・リースについても、原則として資産・負債を計上することが求められる点です。
この改正により、多くの企業で貸借対照表(B/S)が大きく変動し、財務指標にも影響が及ぶ可能性があります。そのため、経理担当者だけでなく、経営層や関連部署も内容を正しく理解し、早期に準備を進めることが重要です。この章では、新リース会計基準の基本的な考え方や改正の背景について、基礎からわかりやすく解説します。
すべてのリースを資産計上する「使用権モデル」
新リース会計基準の核心となる考え方が「使用権モデル」です。これは、借手がリース契約によって得られる「資産を使用する権利」を「使用権資産」として資産に計上し、同時に、将来のリース料支払い義務を「リース負債」として負債に計上するという会計処理モデルです。
これまでの会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、後者は賃貸借処理として費用計上するだけで、資産や負債には計上されませんでした(オフバランス取引)。しかし、新基準ではこの区別が原則として廃止され、短期・少額などの一部の例外を除き、すべてのリース契約が貸借対照表に計上(オンバランス化)されることになります。
| 項目 | 現行のリース会計基準 | 新リース会計基準(公開草案) |
|---|---|---|
| 会計処理モデル | リスク・経済価値アプローチ | 使用権モデル |
| リースの分類(借手) | ファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類 | 原則として区別を廃止 |
| 資産・負債への計上 | ファイナンス・リースのみ計上 | 短期・少額等の例外を除き、すべてのリースを計上 |
| 財務諸表への影響 | オペレーティング・リースはオフバランス処理 | 原則すべてのリースがオンバランス化 |
この変更により、企業の総資産が増加すると同時に負債も増加するため、自己資本比率や負債比率といった財務指標に影響を与えることになります。
なぜリース会計基準は改正されたのか 背景を解説
リース会計基準が改正される最も大きな理由は、会計基準の国際的なコンバージェンス(収斂)です。近年、グローバルに事業展開する企業が増える中で、各国の会計基準が異なると、国外の投資家が企業の財務状況を正しく比較・評価することが困難になるという問題がありました。
特に、日本の現行基準ではオペレーティング・リースがオフバランス処理されるため、多額のリース契約を抱えていても、その実態が貸借対照表に反映されません。これは、投資家から見れば「隠れた負債」であり、企業の財政状態を正確に把握する上での課題とされていました。
そこで、すでに「使用権モデル」を導入している国際財務報告基準(IFRS)や米国会計基準(US-GAAP)との整合性を高め、財務諸表の透明性と国際的な比較可能性を向上させることを目的に、今回の基準改正が進められることになったのです。これにより、投資家は企業のリース利用の実態をより適切に評価できるようになります。
IFRS第16号との関係性
日本の新リース会計基準は、国際財務報告基準(IFRS)の「IFRS第16号『リース』」を基礎として開発されています。IFRS第16号は2019年1月からすでに適用が開始されており、グローバル基準では「使用権モデル」がスタンダードとなっています。
今回の日本の公開草案は、このIFRS第16号の主要な原則をほぼすべて取り入れています。具体的には、借手の会計処理として単一のモデル(使用権モデル)を採用する点や、短期リース・少額リースの免除規定を設ける点などが共通しています。
ただし、完全に同一というわけではなく、日本の会計実務や法制度に配慮した細かな差異や経過措置が設けられる可能性があります。とはいえ、基本的な考え方はIFRS第16号に準拠しており、国際基準への大きな一歩であると理解しておくとよいでしょう。これにより、海外の親会社や投資家への説明責任を果たしやすくなるというメリットも期待できます。
新リース会計基準はいつから適用される?
多くの企業担当者が最も気にするのが、「新リース会計基準がいつから適用されるのか」という点でしょう。結論から言うと、現在公表されている企業会計基準委員会(ASBJ)の公開草案によれば、原則として2026年度から強制適用となる見込みです。ここでは、原則的な適用時期と早期適用について詳しく解説します。
原則的な適用開始時期
日本の新リース会計基準は、2026年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されることが提案されています。例えば、3月決算の企業であれば、2027年3月期の期首である2026年4月1日から適用が開始されます。
この適用時期は、すでに同様の基準を導入しているIFRS(国際財務報告基準)や米国会計基準とのコンバージェンス(収斂)を意識したものであり、グローバルな比較可能性を高める目的があります。上場企業や大会社を中心に、新基準への対応準備が求められます。
| 決算期 | 適用開始日 |
|---|---|
| 2026年3月期 | 旧基準を適用 |
| 2027年3月期 | 2026年4月1日から新基準を強制適用 |
早期適用は可能か
新リース会計基準では、原則適用の開始時期を待たずに、前倒しで基準を適用する「早期適用」も認められる見込みです。公開草案では、2024年4月1日以後開始する事業年度の期首からの早期適用が可能とされています。
特に、親会社がIFRSを適用しており、子会社が日本基準を採用している場合、連結財務諸表を作成する際の手間を軽減するために早期適用を選択するケースが考えられます。ただし、一度早期適用を選択すると、元の会計処理に戻すことはできないため、システム対応や業務フローの変更などを踏まえ、慎重な判断が必要です。
| 適用方法 | 適用開始が可能な事業年度 |
|---|---|
| 原則適用 | 2026年4月1日以後開始する事業年度 |
| 早期適用 | 2024年4月1日以後開始する事業年度 |
自社がいつから対応すべきか、また早期適用を選択するべきかについて、会計監査人とも相談の上、計画的に準備を進めることが重要です。
何が変わる?新旧リース会計基準の変更点を比較
新リース会計基準の導入により、企業の会計実務、特にリース契約の「借手」側の処理が大きく変わります。これまで費用処理のみで済んでいた契約が、資産として計上されることになるため、財務諸表に与える影響は少なくありません。ここでは、従来の基準と新しい基準で具体的に何がどう変わるのかを、借手と貸手の視点から比較し、詳しく解説します。
借手の会計処理 ファイナンスとオペレーティングの区別が廃止
新リース会計基準における最も大きな変更点は、借手側の会計処理です。従来は「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、異なる会計処理を行っていましたが、この区別が原則として廃止され、すべてのリースを資産計上する「使用権モデル」が採用されます。
これまでの会計処理
従来の会計基準では、借手はリース契約をその経済的実態に基づき、以下の2種類に分類していました。
- ファイナンス・リース取引: リース契約が実質的に資産の購入と資金の借入れと見なされる取引です。リース物件の所有権が移転する、割安購入選択権があるなどの条件を満たす場合に該当し、リース資産とリース負債を貸借対照表(BS)に計上する「オンバランス処理」が行われます。
- オペレーティング・リース取引: ファイナンス・リース以外のリース取引で、一般的な賃貸借契約と同様に扱われます。支払ったリース料を費用として損益計算書(PL)に計上するだけで、資産や負債は計上されない「オフバランス処理」が行われます。
新リース会計基準の会計処理
新しいリース会計基準では、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区別がなくなり、原則としてすべてのリース契約について、資産と負債を計上することになります。具体的には、借手はリース開始日に、リース物件を使用する権利を「使用権資産」、将来のリース料支払い義務を「リース負債」として、それぞれ貸借対照表(BS)に計上します。
これにより、これまでオフバランス処理されていたオペレーティング・リースもBSに計上されるため、企業の総資産や負債の額が大きくなり、財務状況がより実態に即して表示されるようになります。
新旧の会計処理の違いをまとめると、以下のようになります。
| 項目 | 旧基準(ファイナンス・リース) | 旧基準(オペレーティング・リース) | 新基準(原則すべてのリース) |
|---|---|---|---|
| 貸借対照表(BS)への計上 | リース資産とリース負債を計上(オンバランス) | 計上しない(オフバランス) | 使用権資産とリース負債を計上(オンバランス) |
| 損益計算書(PL)への計上 | 減価償却費と支払利息 | 支払リース料 | 減価償却費と支払利息 |
貸手の会計処理は原則として変更なし
借手側の会計処理が大きく変わる一方で、リース契約の「貸手」側の会計処理は、現行の会計基準が基本的に維持されることになります。これは、国際的な会計基準であるIFRS第16号でも貸手の会計処理は大きく変更されなかった点を踏襲しているためです。
したがって、貸手は引き続き、リース契約を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、それぞれに応じた会計処理を行います。自社が貸手となる取引については、これまで通りの実務を継続することになります。
対象となるリースの定義
新リース会計基準では、会計処理の対象となる「リース」の定義もより明確化されます。新基準におけるリースとは、「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約、または契約の一部」と定義されます。
ある契約がリースに該当するかどうかを判断するための重要なポイントは、以下の2つです。
- 識別された資産の存在: 契約の対象となる資産が、物理的に特定されている、または顧客がその資産の能力の大部分を使用する権利を有しているなど、明示的または黙示的に特定されていること。
- 使用を支配する権利の移転: 契約期間を通じて、顧客(借手)が特定された資産の使用を指図し、その使用から得られる経済的便益のほとんどすべてを享受する権利を有していること。
この定義により、これまでリースとして認識されていなかったIT関連のサービス契約(クラウドサービスなど)や業務委託契約の一部が、新基準ではリース契約に該当すると判断される可能性があります。そのため、企業は既存の契約内容を改めて見直し、新基準におけるリースの定義に該当するかどうかを慎重に検討する必要があります。
【仕訳例】新リース会計基準の具体的な会計処理
新リース会計基準の最も大きな変更点の一つが、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースも、原則として貸借対照表(B/S)に資産・負債として計上(オンバランス)される点です。ここでは、具体的な数値例を用いて、リース開始時から決算時までの会計処理の流れを仕訳で確認していきましょう。
以下の条件でリース契約を締結した場合を想定します。
| リース対象 | 事務用コピー機 |
|---|---|
| リース期間 | 5年 |
| 年間リース料 | 100万円(後払い) |
| 割引率 | 3%(借手の追加借入利子率) |
| 所有権移転条項 | なし |
リース開始時の仕訳 リース資産とリース負債の計上
リース契約を開始する際、借手はまず将来支払うリース料総額の現在価値を計算し、その金額を「使用権資産」および「リース負債」として貸借対照表に計上します。
現在価値の計算は、各期のリース料を契約時に定めた割引率で割り引くことで算出します。今回のケースでは、年間リース料100万円、期間5年、割引率3%の年金現価係数(4.5797)を用いて計算します。
計算式:1,000,000円 × 4.5797 = 4,579,700円
この計算結果に基づき、リース開始時には以下の仕訳を行います。これにより、貸借対照表の資産の部に「使用権資産」が、負債の部に「リース負債」がそれぞれ計上されます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 使用権資産 | 4,579,700 | リース負債 | 4,579,700 |
決算時の仕訳 減価償却費と支払利息
決算時には、計上した「使用権資産」と「リース負債」に対して、それぞれ会計処理が必要です。具体的には、使用権資産の「減価償却」と、リース負債に係る「支払利息の計上および元本の返済」を行います。
使用権資産の減価償却
使用権資産は、原則としてリース期間にわたって定額法で減価償却を行います。これにより、資産の使用による価値の減少を費用として認識します。
計算式:4,579,700円 ÷ 5年 = 915,940円
決算整理仕訳として、以下の仕訳を行います。この減価償却費は、損益計算書(P/L)上で販売費及び一般管理費などに計上されます。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 915,940 | 使用権資産減価償却累計額 | 915,940 |
リース負債の利息と返済
リース料の支払いには、利息の支払いと元本(リース負債)の返済が含まれています。決算時には、利息法を用いて支払利息を計算し、リース料の支払いと合わせて処理します。
1年目の支払利息の計算
計算式:期首リース負債残高 4,579,700円 × 割引率 3% = 137,391円
1年目の元本返済額の計算
計算式:年間リース料 1,000,000円 − 支払利息 137,391円 = 862,609円
リース料支払時には、以下の仕訳を行います。従来のオペレーティング・リースでは「支払リース料」として全額費用処理されていましたが、新基準では「支払利息(営業外費用)」と「リース負債の返済」に分けて処理される点が大きな違いです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| リース負債 | 862,609 | 現金預金 | 1,000,000 |
| 支払利息 | 137,391 |
この結果、1年目終了時点でのリース負債の期末残高は、期首残高から元本返済額を差し引いた 3,717,091円(4,579,700円 – 862,609円)となります。翌期以降も、この期末残高を元に同様の計算を繰り返していきます。
企業実務への影響と必要な対応
新リース会計基準の導入は、単に会計処理が変わるだけではありません。企業の財務数値や経営指標、さらには業務プロセス全体にまで広範な影響を及ぼします。ここでは、具体的な影響と、経理担当者をはじめとする企業が今から準備すべきことについて詳しく解説します。
財務諸表に与える影響
新リース会計基準の最も大きな影響は、これまでオフバランス処理(貸借対照表に計上されない)が可能であったオペレーティング・リースが、原則としてオンバランス化(資産・負債として計上)される点です。これにより、財務諸表の各項目が以下のように変動します。
| 財務諸表 | 主な影響 | 詳細 |
|---|---|---|
| 貸借対照表(B/S) | 総資産と負債の増加 |
新たに「使用権資産」が資産として、「リース負債」が負債として計上されます。これにより、企業のバランスシートが大きく膨らむことになります。 |
| 損益計算書(P/L) | 費用の内訳と計上時期の変更 |
従来の「支払リース料」という単一の費用科目が、「減価償却費」(使用権資産の償却)と「支払利息」(リース負債に係る利息)に分かれます。費用総額は変わりませんが、リース期間の初期に費用が厚く計上される傾向があります。 |
| キャッシュフロー計算書(C/F) | 表示区分の変更 |
リース料の支払いが、利息部分(営業CF)と元本返済部分(財務CF)に区分されます。これにより、営業キャッシュフローは増加し、財務キャッシュフローは減少するという見え方の変化が生じます。 |
これらの変動は、企業の財務指標にも直接的な影響を与えます。例えば、総資産が増加するためROA(総資産利益率)が低下したり、リース負債が有利子負債として扱われることで自己資本比率やD/Eレシオが悪化したりする可能性があります。金融機関との融資契約における財務制限条項(コベナンツ)に抵触しないか、事前の確認と対策が不可欠です。
経理担当者が準備すべきこと
新リース会計基準への対応は、経理部門だけの問題ではなく、全社的なプロジェクトとして捉える必要があります。適用開始に向けて、以下のステップで準備を進めることが推奨されます。
ステップ1:社内すべてのリース契約の網羅的な把握
まずは、社内に存在するすべてのリース契約を洗い出し、管理台帳を整備することから始めます。これには、コピー機のリースといった典型的なものだけでなく、これまで費用処理していた不動産の賃貸借契約やIT機器のレンタル契約なども含まれます。契約書を精査し、新基準における「リース」の定義に該当するかどうかを一つひとつ判断するという、地道ですが非常に重要な作業です。
ステップ2:会計方針の決定
次に、自社の状況に合わせて具体的な会計方針を決定します。主に検討すべき項目は以下の通りです。
- 適用初年度の経過措置:新基準を過去に遡って完全に適用する方法と、適用開始日からの影響のみを反映させる簡便的な方法のどちらを選択するかを決定します。
- 割引率の算定方法:リース負債の計算に用いる割引率(追加借入利子率など)を、どのように算定するかのルールを明確にします。
- 簡便法の適用範囲:短期リースや少額リースについて、資産計上を免除する簡便的な取扱いを適用するか、またその場合の金額基準などを決定します。
ステップ3:業務プロセスとシステムの再構築
新基準では、リース契約ごとに使用権資産とリース負債を算出し、減価償却費や支払利息を計算して管理する必要があります。契約件数が多い企業では、Excelでの管理には限界があるため、会計システムや固定資産管理システムの改修、またはリース資産管理に特化したツールの導入が必須となるでしょう。契約管理から会計処理、開示資料作成までの一連の業務フローを見直す必要があります。
ステップ4:関係部署との連携体制の構築
リース契約は、総務、法務、IT、営業など、社内の様々な部署が関与しています。新基準へのスムーズな移行のためには、これらの関係部署と密に連携し、新規契約時の情報共有ルールなどを定めておくことが重要です。また、財務指標への影響について経営層や財務部門と共有し、投資家や金融機関への説明準備も進めておく必要があります。
中小企業向けの簡便的な取扱い
大企業に比べて経理体制が脆弱な中小企業にとって、新リース会計基準への対応は大きな負担となり得ます。そのため、日本の会計基準(J-GAAP)では、中小企業の実務負担を軽減するための簡便的な取扱いが設けられる見込みです。
具体的には、「中小企業の会計に関する指針」の適用対象となる企業については、当面の間、重要なリース契約を除き、従来通りの賃貸借処理を継続することが認められる方向で検討が進められています。これにより、多くの中小企業は、直ちに新基準の複雑な会計処理へ移行する必要はなくなると考えられます。
ただし、自社がその対象となるか、また将来的な基準の変更の可能性もあるため、常に最新の情報を確認し、公認会計士や税理士などの専門家に相談することが賢明です。
新リース会計基準でよくある質問 Q&A
新リース会計基準の導入にあたり、多くの経理担当者様が抱えるであろう疑問点について、Q&A形式でわかりやすく解説します。実務で判断に迷いやすいポイントを中心にまとめました。
Q1. 短期リースや少額リースの扱いはどうなる?
すべてのリース契約を資産計上する原則には、実務上の負担を軽減するための「例外規定」が設けられています。具体的には、「短期リース」と「少額リース」については、これまで通りの賃貸借処理(費用計上)を継続することが認められます。これは強制ではなく、企業が会計方針として選択適用できます。
短期リース
リース期間が12ヶ月以内のリースを指します。例えば、展示会のために3日間だけ借りるイベント機材や、繁忙期に6ヶ月間だけレンタルするPCなどが該当します。ただし、購入オプションが付いているなど、実質的に12ヶ月を超えて使用する可能性が高い契約は対象外となるため注意が必要です。
少額リース
リースする資産そのものの価値が低いリースを指します。例えば、オフィスで利用するコピー機やウォーターサーバー、個々のPCなどが該当する可能性があります。どのくらいの金額までを「少額」とするかについて、日本の会計基準では明確な金額基準は示されていませんが、IFRS(国際財務報告基準)では新品時の価額が5,000米ドル以下という目安が示されており、これが一つの参考になると考えられます。
| 種類 | 定義 | 会計処理 | 具体例 |
|---|---|---|---|
| 短期リース | リース期間が12ヶ月以内のリース | 使用権資産・リース負債を計上せず、リース料を費用処理できる | ・イベント用の短期レンタル什器 ・プロジェクト用の半年契約のPC |
| 少額リース | リース対象資産の新品価額が少額であるリース | 使用権資産・リース負債を計上せず、リース料を費用処理できる | ・タブレット端末 ・オフィス家具 ・電話機 |
これらの簡便的な取扱いを選択することで、多数の少額なリース契約を管理する手間を大幅に削減できます。
Q2. 既存のリース契約はどうすればいい?
新リース会計基準の適用開始日より前から契約しているリースについては、経過措置として、原則的なアプローチと簡便的なアプローチのいずれかを選択適用できます。
原則的なアプローチ(遡及適用)
過去の財務諸表を、まるで当初から新基準を適用していたかのように修正する方法です。比較可能性は高まりますが、過去の契約すべてについて再計算が必要となるため、実務上の負担は非常に大きくなります。
簡便的なアプローチ(修正遡及アプローチ)
実務上の負担を考慮して認められている方法です。適用開始日に、既存のリース契約について残りのリース期間とリース料を基にリース負債と使用権資産を計上します。過去の財務諸表を修正する必要がないため、多くの企業がこの方法を選択すると予想されます。
具体的には、適用初日において、オペレーティング・リースについて以下の処理を行います。
- 残りのリース料総額を、適用初日時点の追加借入利子率で割り引いて「リース負債」を計算します。
- 原則として、計算したリース負債と同額を「使用権資産」として計上します。
この簡便法により、過去に遡って複雑な計算を行うことなく、新基準へスムーズに移行することが可能です。
Q3. 中小企業や非上場企業にも適用される?
新リース会計基準は、上場企業や会社法上の大会社などを対象として開発が進められています。そのため、「中小企業の会計に関する指針」や「中小企業の会計に関する基本要領」の適用対象となる中小企業については、引き続き従来の賃貸借処理が認められる見込みです。
ただし、非上場であっても、将来的な上場を目指している企業や、連結子会社として親会社(上場企業)の会計方針に合わせる必要がある企業は、新基準への対応を準備しておく必要があります。自社がどの会計基準の対象となるか、顧問税理士や会計士に確認することが重要です。
Q4. リース期間はどのように算定する?
リース期間の算定は、使用権資産とリース負債の金額を決定する上で非常に重要な要素です。新基準では、リース期間を「解約不能期間」に加えて、「借手が延長オプションを行使することが合理的に確実な期間」と「借手が解約オプションを行使しないことが合理的に確実な期間」を含めて決定します。
例えば、3年間の解約不能期間の契約で、その後2年間の延長オプションが付いているとします。過去の実績や事業計画から、その延長オプションを行使する可能性が非常に高いと判断される場合、リース期間は「5年(3年+2年)」として計算する必要があります。
「合理的に確実」かどうかの判断には、以下のような経済的インセンティブを総合的に勘案する必要があります。
- 解約した場合に発生する違約金の額
- リース資産に重要な改良を加えているか
- 代替資産を見つけることの困難性
- 市場のリース料との比較
これまで以上に、契約内容の詳細な検討と、将来の事業計画に基づいた合理的な判断が求められます。
Q5. 変動リース料はリース負債に含まれる?
リース料には、毎月定額の固定リース料のほかに、売上高や使用量に応じて変動する「変動リース料」が含まれる場合があります。新基準では、変動リース料のうち、リース負債の測定に含めるものと含めないものが明確に区別されます。
| 変動要因 | リース負債への算入 | 会計処理 |
|---|---|---|
| 指数・レート(例:消費者物価指数、市場金利) | 含める | 当初はリース開始時点の指数・レートで計算。変動時にリース負債と使用権資産を修正。 |
| 売上高・使用量(例:売上の〇%、走行距離1kmあたり〇円) | 含めない | 発生した事業年度の費用として処理する。(支払リース料など) |
例えば、商業施設の店舗賃料が「最低保証家賃+売上歩合」で構成されている場合、最低保証家賃の部分はリース負債に含めますが、売上歩合の部分は含めません。売上歩合家賃は、発生した都度、費用として計上することになります。契約内容をよく確認し、どのリース料が負債計上の対象となるかを見極めることが重要です。
まとめ
本記事では、新リース会計基準の概要から変更点、実務への影響までを図解を交えて解説しました。新リース会計基準の最大のポイントは、国際的な会計基準であるIFRS第16号との整合性を図る目的で、原則としてすべてのリースを資産・負債として計上する「使用権モデル」が採用される点です。これにより、企業の財務状況の透明性が高まります。
この変更によって、借手側ではこれまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースも貸借対照表に計上されることになります。その結果、総資産と負債がともに増加し、自己資本比率などの財務指標に影響を及ぼす可能性があります。貸手側の会計処理に原則として大きな変更はありません。
新基準の適用に向けて、経理担当者は自社が契約しているリース契約の全体像を把握し、会計システムの見直しや業務フローの再構築といった準備を計画的に進める必要があります。ただし、短期リースや少額リースには簡便的な処理が認められているため、自社の状況と照らし合わせながら、着実に対応を進めていきましょう。
【PR】関連サイト
株式会社プロシップ
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル 9F
URL:https://www.proship.co.jp/