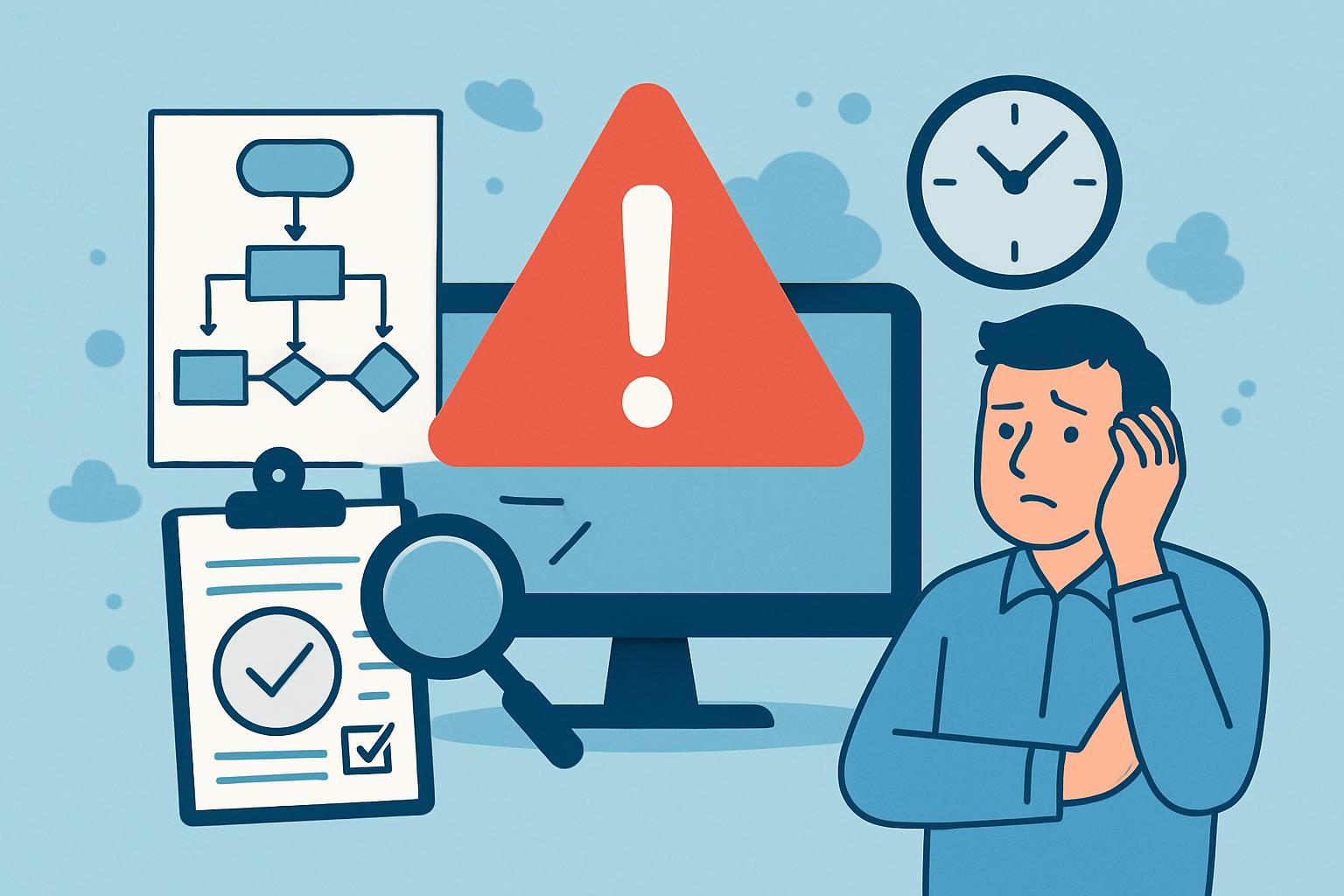突然のシステム障害やサービス停止といったインシデントへの対応に追われ、業務が滞っていませんか?インシデント管理の成功の鍵は、確立されたフローと適切な報告体制を構築し、迅速なサービス復旧を実現することです。この記事では、インシデント管理の目的や問題管理との違いといった基礎知識から、ITILに準拠した具体的な7ステップのフロー図、コピーしてすぐに使える報告書テンプレートまでを網羅的に解説します。さらに、管理体制を成功させるポイントや、Jira Service Managementなどのおすすめツールも紹介。この記事を読めば、インシデント対応の属人化を防ぎ、サービスを迅速に復旧させるための具体的な手順と仕組み作りがわかります。
インシデント管理とは 目的と重要性をわかりやすく解説
インシデント管理とは、ITサービスの利用中に発生するシステム障害やパフォーマンスの低下といった「インシデント」に対して、迅速にサービスを正常な状態に復旧させ、ビジネスへの影響を最小限に抑えるためのプロセスです。現代のビジネスにおいてITシステムは事業の根幹を支える重要な要素であり、ひとたび停止すれば売上の機会損失や顧客からの信頼失墜に直結します。そのため、インシデントをいかに素早く検知し、適切に対処するかを定めたインシデント管理は、安定したサービス提供に不可欠な活動と言えます。
ここで言う「インシデント」とは、サービスの予期せぬ中断や品質の低下を引き起こす、あるいは引き起こす可能性のある、計画外の出来事を指します。例えば、「サーバーがダウンしてウェブサイトにアクセスできない」「アプリケーションの動作が極端に遅い」「決済処理でエラーが発生する」といった事象がこれにあたります。
インシデントと問題管理の違い
インシデント管理を理解する上で、よく混同される「問題管理」との違いを明確にすることが重要です。両者は密接に関連していますが、その目的と役割は異なります。インシデント管理は「応急処置」であり、問題管理は「根本治療と再発防止」と考えると分かりやすいでしょう。
例えば、火事で例えるなら、まず火を消す活動がインシデント管理にあたります。一方、火事の原因(漏電など)を調査し、二度と火事が起きないように対策するのが問題管理です。両者の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | インシデント管理 | 問題管理 |
|---|---|---|
| 目的 | サービスの迅速な復旧 | インシデントの根本原因の特定と恒久的な解決 |
| ゴール | ビジネスへの影響を最小限に抑える(応急処置) | 将来的なインシデントの発生を未然に防ぐ(再発防止) |
| 主な活動 | インシデントの記録、分類、優先順位付け、エスカレーション、解決、クローズ | 根本原因分析(RCA)、既知のエラーの記録、恒久的な解決策の策定と実装 |
| 時間軸 | 即時性・緊急性が高い | 中長期的・分析的 |
このように、インシデント管理は目の前で起きている事象への対処に焦点を当て、一刻も早くサービスを使える状態に戻すことを最優先します。そのインシデントがなぜ起きたのかを深く掘り下げるのは、問題管理のプロセスに引き継がれます。
インシデント管理の目的は迅速なサービス復旧
インシデント管理の最大の目的は、前述の通り「できる限り迅速にサービスを正常な状態へ復旧させること」です。この目的を達成することにより、企業は以下のようなメリットを得ることができます。
- ビジネスへの影響の最小化: サービス停止時間を短縮することで、売上機会の損失や生産性の低下を防ぎます。
- 顧客満足度の維持・向上: ユーザーがサービスを利用できない時間を短くし、不満や不信感を軽減します。迅速で誠実な対応は、かえって顧客の信頼を高めることにも繋がります。
- IT部門の生産性向上: 対応手順が標準化されることで、担当者は場当たり的な対応から解放され、より効率的にインシデントを処理できます。これにより、他の重要な業務に時間を割くことが可能になります。
重要なのは、インシデント管理のフェーズでは「根本原因の特定」に固執しないことです。原因究明に時間をかけすぎると、その間サービスが停止し続け、ビジネスへのダメージが拡大してしまいます。まずは暫定的な対策(ワークアラウンド)でも構わないので、サービスを復旧させることを最優先に行動します。
ITILにおけるインシデント管理の役割
ITIL(Information Technology Infrastructure Library)は、ITサービスマネジメントにおける成功事例(ベストプラクティス)を体系的にまとめた世界的なフレームワークです。多くの企業がITILを参考に、自社のITサービス運用プロセスを構築・改善しています。
ITILのライフサイクルの中で、インシデント管理は日々のITサービス運用を担う「サービスオペレーション」段階における中核的なプロセスとして位置づけられています。ITILにおけるインシデント管理は、標準化されたプロセスに従ってインシデントを管理し、サービスの可用性と品質を維持することを目的としています。
また、インシデント管理は単独で機能するものではなく、他のITILプロセスと密接に連携します。
- 問題管理: 解決したインシデントの情報を問題管理プロセスに引き渡し、根本原因の分析と再発防止策の検討を依頼します。
- 変更管理: インシデントの解決にシステムの変更が必要な場合、変更管理プロセスを通じてリスクを評価し、計画的に変更を実施します。
- 構成管理: インシデントが発生したIT資産(サーバー、ネットワーク機器など)の情報を構成管理データベース(CMDB)から参照し、迅速な原因調査に役立てます。
このように、ITILのフレームワークに沿ってインシデント管理を運用することで、属人化を防ぎ、組織として一貫性のある高品質な対応を実現できるのです。
業務を効率化するインシデント管理の基本フロー
インシデント管理を場当たり的に行うと、対応が属人化し、解決までの時間が長引く原因となります。標準化されたフローを確立し、組織全体で共有することが、業務の効率化とサービス品質の向上に不可欠です。一貫したプロセスは、対応の抜け漏れを防ぎ、誰が対応しても一定の品質を保つことを可能にします。
【フロー図で解説】インシデント管理の7ステップ
インシデント管理は、インシデントの発生から解決、そしてクローズまでの一連の流れを体系化したものです。ここでは、ITIL(IT Infrastructure Library)でも推奨されている、最も基本的で重要な7つのステップを解説します。このフローに沿って対応することで、迅速かつ的確なインシデント解決が実現できます。
ステップ1 インシデントの検知と記録
インシデント管理の第一歩は、インシデントの発生を「検知」し、その内容を正確に「記録」することです。検知は、ユーザーからの電話やメール、チャットによる問い合わせのほか、監視ツールからの自動アラートなど、さまざまなチャネルを通じて行われます。どのような些細な事象であっても、すべてのインシデントを管理ツールに漏れなく記録することが、後の分析や恒久的な対策の基礎となります。記録する際には、発生日時、報告者、連絡先、インシデントの内容、発生しているシステムやサービスなどの情報を正確に残しましょう。
ステップ2 分類と初期サポート
記録されたインシデントは、次に「分類」されます。例えば、「ハードウェア障害」「ソフトウェアの不具合」「ネットワーク関連」「操作方法の問い合わせ」といったカテゴリに分けることで、どの専門チームが対応すべきかを迅速に判断できます。分類後、サービスデスクの担当者が一次対応として「初期サポート」を行います。過去の類似インシデントをナレッジベースで検索し、既知の解決策で対応することで、多くのインシデントをこの段階で迅速に解決できます。これにより、専門チームの負担を軽減し、組織全体の対応効率を高めることができます。
ステップ3 優先度の決定
すべてのインシデントに同時に対応することは不可能です。そのため、ビジネスへの影響度と緊急度を基に「優先度」を決定し、対応の順序を決めます。影響度は「何人のユーザーに影響が出ているか」、緊急度は「ビジネス活動がどの程度妨げられているか」といった観点で評価します。客観的な基準で優先度を決定することで、対応の属人化を防ぎ、最も重要なインシデントから着手することが可能になります。
| 緊急度:高 (基幹業務が停止) | 緊急度:中 (一部業務に支障) | 緊急度:低 (代替手段あり) | |
|---|---|---|---|
| 影響度:大 (全部門に影響) | 優先度:1 (最高) | 優先度:2 (高) | 優先度:3 (中) |
| 影響度:中 (特定部門に影響) | 優先度:2 (高) | 優先度:3 (中) | 優先度:4 (低) |
| 影響度:小 (特定個人に影響) | 優先度:3 (中) | 優先度:4 (低) | 優先度:5 (最低) |
ステップ4 調査と診断
初期サポートで解決しなかったインシデントは、専門知識を持つ二次担当者によって詳細な「調査と診断」が行われます。このステップでは、ログファイルの解析、再現テスト、システム設定の確認などを通じて、インシデントの根本原因を特定します。正確な原因究明が、場当たり的ではない適切な解決策の選択と、将来的な再発防止につながります。調査の進捗状況は、関係者やユーザーへ適宜報告することが重要です。
ステップ5 エスカレーション
担当者のスキルや権限では解決が困難な場合、より上位の専門家や管理者、あるいは外部のベンダーへ対応を引き継ぐ「エスカレーション」を行います。エスカレーションには、より専門的な技術を持つ担当者へ引き継ぐ「機能的エスカレーション」と、SLA(サービスレベル合意書)で定められた解決時間を超えそうな場合に管理者へ報告する「階層的エスカレーション」があります。事前に明確なエスカレーションルールを定めておくことで、対応の停滞を防ぎ、問題解決までの時間を大幅に短縮できます。
ステップ6 解決と復旧
原因が特定され、解決策が明らかになったら、システムを正常な状態に戻すための「解決と復旧」作業を実施します。これには、ソフトウェアのアップデート、設定の変更、ハードウェアの交換などが含まれます。作業完了後は、必ずインシデントを報告したユーザーに連絡を取り、問題が解決してサービスが正常に利用できることを確認してもらいます。この最終確認をもって、サービスが完全に復旧したと判断します。
ステップ7 インシデントのクローズ
ユーザーから解決の合意を得た後、インシデント管理プロセスは最終段階である「クローズ」に移ります。この段階では、インシデントの発生から解決までのすべての対応履歴、原因、実施した解決策を管理ツールに最終記録します。対応記録をナレッジとして整理・蓄積し、組織全体で共有することが、将来発生する同様のインシデントへの迅速な対応を可能にし、組織のインシデント対応能力を継続的に向上させます。これで一連のインシデント対応は完了です。
【コピーしてすぐ使える】インシデント管理報告書のテンプレート
インシデントが発生した際、その内容を正確に関係者へ共有し、将来の再発防止に繋げるために不可欠なのが「インシデント管理報告書」です。しかし、いざ作成するとなると「何を書けば良いのかわからない」と悩む方も少なくありません。この章では、コピーしてすぐに使える報告書のテンプレートと、作成のポイントを具体的に解説します。
インシデント管理報告書に含めるべき必須項目
インシデント管理報告書は、誰が読んでも状況を正確に理解できるよう、客観的な事実を過不足なく記載する必要があります。以下の必須項目を網羅することで、情報共有の漏れを防ぎ、原因分析と再発防止策の検討をスムーズに進めることができます。
| 項目名 | 内容 | 記載のポイント |
|---|---|---|
| 管理番号 | インシデントを識別するための一意の番号 | 「INC-日付-連番」のように命名規則を定めると管理しやすくなります。 |
| 報告日 | 報告書を作成した日付 | 最終更新日と区別し、初版の作成日を記載します。 |
| 報告者 | 報告書を作成した担当者の部署・氏名 | 問い合わせ先を明確にします。 |
| 発生日時 | インシデントが最初に発生した正確な日時 | 原因究明の重要な手がかりとなります。不明な場合は検知日時を記載します。 |
| 復旧日時 | サービスやシステムが正常な状態に復旧した日時 | ダウンタイムの算出やSLAへの影響度評価に必要です。 |
| インシデント概要 | 何が起きたのかを簡潔にまとめた説明 | 専門知識がない人でも理解できるよう、5W1Hを意識して分かりやすく記述します。 |
| 影響範囲 | インシデントによる影響を受けたシステム、サービス、顧客、部署など | 影響の大きさを具体的に(例:「顧客A社の○○システム」「全社のファイルサーバー」)記載します。 |
| 発生原因 | インシデントを引き起こした根本的な原因 | 直接的な原因(トリガー)と、その背景にある根本原因(例:設定ミス、リソース不足)を分けて分析・記載します。 |
| 対応経緯(時系列) | 検知から復旧までの対応内容を時系列で記録 | 「誰が」「いつ」「何をしたか」を具体的に記述し、対応の正当性や改善点を後から検証できるようにします。 |
| 暫定対応 | サービスを復旧させるために実施した応急処置 | 恒久対応と区別し、どのような応急処置を行ったかを記録します。 |
| 恒久対応(再発防止策) | 根本原因を解決し、再発を防ぐための具体的な対策 | 「注意する」といった曖昧な表現は避け、「誰が」「いつまでに」「何をするか」を明確に記述します。 |
| 関係者 | 本インシデントの対応に関わった担当者や報告先 | 情報共有の範囲を明確にし、責任の所在を明らかにします。 |
報告書の例文と書き方のポイント
ここでは、上記の必須項目に基づいたインシデント管理報告書の例文を紹介します。自社のフォーマットに合わせて適宜修正し、ご活用ください。
インシデント管理報告書 例文
管理番号: INC-20231027-001
報告日: 2023年10月28日
報告者: システム開発部 鈴木 一郎
発生日時: 2023年10月27日 14:30頃
復旧日時: 2023年10月27日 16:00
インシデント概要:
公式ウェブサイトのトップページが表示されなくなり、顧客がサービスにアクセスできない状態となった。
影響範囲:
・公式ウェブサイト(www.example.co.jp)を利用する全てのユーザー
・影響時間:約90分間
発生原因:
【直接原因】Webサーバー(Web-01)のアプリケーションプロセスが応答不能状態に陥ったため。
【根本原因】10月27日14:00にリリースした新機能のプログラムにメモリリークの不具合があり、サーバーリソースを想定以上に消費したことが原因。
対応経緯(時系列):
・14:35:監視システムよりWebサーバーの異常検知アラートを受信。担当者が調査を開始。
・14:45:Webサーバーへのアクセスがタイムアウトすることを確認。インシデントと判断し、関係各所へ第一報を連絡。
・15:10:サーバーログを調査し、特定のアプリケーションプロセスに起因するメモリ使用量の急増を確認。
・15:30:暫定対応として、該当プロセスの再起動を実施するも、状況が改善せず。
・15:45:原因が同日リリースの新機能にあると特定。当該機能をロールバック(切り戻し)することを決定。
・16:00:ロールバック作業が完了し、ウェブサイトが正常に表示されることを確認。サービス復旧を宣言。
暫定対応:
新機能のデプロイメントをロールバックし、インシデント発生前の安定バージョンに戻した。
恒久対応(再発防止策):
1. 【修正】メモリリークを引き起こしたプログラムコードの修正(担当:佐藤、期限:11/2)
2. 【テスト強化】リリース前の負荷テスト項目に、メモリ使用量の長期的な監視を追加(担当:開発チーム、期限:次期リリースより適用)
3. 【手順見直し】重大な機能リリースの際は、段階的リリース(カナリアリリース)を導入し、影響範囲を限定する手順を策定(担当:高橋、期限:11/30)
関係者:
システム開発部、インフラ運用部、カスタマーサポート部
報告書を作成する際は、客観的な事実のみを時系列に沿って記述し、個人の憶測や感情を含めないことが重要です。また、専門用語の使用は避け、IT部門以外の経営層や他部署の担当者が見ても理解できる平易な言葉で書くことを心がけましょう。これにより、全社的な情報共有とスムーズな意思決定を促進します。
インシデント管理を成功させる3つのポイント
インシデント管理のフローを導入し、報告書を作成するだけでは、業務効率化は実現しません。重要なのは、その仕組みを組織全体で効果的に運用し、継続的に改善していくことです。ここでは、インシデント管理を形骸化させず、成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。
ポイント1 明確な役割分担と体制構築
インシデントが発生した際、誰が何をするのかが曖昧では、対応の遅れや混乱を招き、被害が拡大する恐れがあります。迅速かつ的確な対応を実現するためには、事前に役割と責任を明確にし、スムーズに連携できる体制を構築しておくことが不可欠です。
具体的には、インシデントの受付からクローズまでの一連のプロセスにおいて、各担当者の役割を定義します。一般的には、以下のような役割が考えられます。
| 役割 | 主な責務 | 担当部署・担当者の例 |
|---|---|---|
| インシデントマネージャー | インシデント管理プロセス全体の責任者。対応の指揮、進捗管理、関係者への報告を行う。 | 情報システム部門のリーダー、チームマネージャー |
| 一次対応担当者(サービスデスク) | インシデントの最初の窓口。内容のヒアリング、記録、分類、既知の解決策での対応を行う。 | ヘルプデスク、コールセンターのオペレーター |
| 二次対応担当者(専門チーム) | 一次対応で解決できない、より専門的な調査や診断、復旧作業を行う。 | サーバー担当、ネットワーク担当、アプリケーション開発担当 |
| エスカレーション先 | 二次対応でも解決が困難な場合や、経営判断が必要な重大インシデントの場合の報告・相談先。 | 部門長、役員、外部の専門ベンダー |
これらの役割を自社の組織体制に合わせて定義し、緊急連絡網や報告ルートを整備しておきましょう。特に24時間365日の対応が求められるシステムの場合は、シフト体制やオンコール(緊急時呼び出し)担当者を決めておくことが重要です。誰が見ても担当者と連絡先がわかる体制図を作成し、常に最新の状態に保つことを心がけてください。
ポイント2 SLA(サービスレベル合意書)の設定
SLA(Service Level Agreement)とは、サービスの提供者と利用者の間で、サービスの品質レベルについて合意したものです。インシデント管理においてSLAを設定することで、対応の目標が明確になり、客観的な基準に基づいて優先順位を判断できるようになります。
SLAには、主に以下の項目を定義します。
- サービス提供時間: サービスデスクが対応可能な時間帯(例: 平日9:00~18:00)
- 目標応答時間: インシデントの報告を受けてから、一次対応を開始するまでの目標時間
- 目標復旧時間(RTO): インシデント発生から、サービスを復旧させるまでの目標時間
特に目標復旧時間は、インシデントの「優先度」に応じて設定することが重要です。優先度は、事業への影響度を示す「インパクト」と、対応の緊急性を示す「緊急度」の2つの軸を組み合わせて決定するのが一般的です。
優先度決定のマトリクス例
| 緊急度:高 (すぐに解決が必要) | 緊急度:中 (計画的な対応が可能) | 緊急度:低 (時間的余裕がある) | |
|---|---|---|---|
| インパクト:大 (基幹システム停止など) | 最優先 | 高 | 中 |
| インパクト:中 (一部機能の停止など) | 高 | 中 | 低 |
| インパクト:小 (軽微な不具合など) | 中 | 低 | 低 |
このようにSLAと優先度を定義することで、「どのインシデントから対応すべきか」という判断基準が明確になり、限られたリソースを重要なインシデントに集中させることができます。また、サービス利用者にとっても「いつまでに解決されるのか」という見通しが立つため、満足度の向上にも繋がります。
ポイント3 ナレッジベースの活用と継続的な改善
発生したインシデントへの対応履歴は、組織にとって貴重な財産です。これらの情報をナレッジベースとして蓄積・活用することで、インシデント管理の品質と効率を飛躍的に向上させることができます。
インシデントを単なる「点」で終わらせず、組織の「資産」として蓄積・活用し、将来のインシデント対応に活かす仕組みを構築することが成功のカギです。この考え方は、KCS(ナレッジセンターサービス)とも呼ばれ、ナレッジを積極的に活用する文化を醸成します。
ナレッジベース活用の具体的な取り組みは以下の通りです。
- 対応履歴の記録と共有: インシデントの原因、調査過程、解決策を詳細に記録し、誰でも検索・参照できるデータベースを構築します。これにより、過去に類似のインシデントが発生した場合、迅速に解決策を見つけ出すことができます。
- FAQやマニュアルの整備: よくある質問や簡単なトラブルシューティング手順をFAQとしてまとめることで、利用者自身による自己解決を促し、サービスデスクへの問い合わせ件数を削減します。
- 継続的な改善活動(CSI): インシデント対応完了後にレビュー(PIR: Post Incident Review)を行い、対応プロセスの問題点や改善点を洗い出します。また、蓄積されたインシデントデータを分析し、発生頻度の高いインシデントの根本原因を特定して「問題管理」プロセスに連携することで、再発防止に繋げます。
ナレッジベースを整備することで、担当者のスキルレベルに依存しない安定した対応品質を維持し、属人化を防ぐことができます。インシデント対応のたびにナレッジを更新し、常に最新で役立つ情報が蓄積されるサイクルを作り上げましょう。
おすすめのインシデント管理ツール3選
インシデント管理のプロセスを効率的に運用するには、ツールの活用が欠かせません。インシデントの記録、担当者の割り当て、進捗状況の可視化、ナレッジの蓄積といった一連の業務をツールで一元管理することで、対応の迅速化と品質向上が期待できます。ここでは、国内外で実績があり、多くの企業で導入されている代表的なインシデント管理ツールを3つ厳選してご紹介します。
多機能で連携に強い Jira Service Management
Jira Service Managementは、アトラシアン社が提供するITサービスマネジメント(ITSM)ツールです。特に、アジャイル開発チームで広く利用されている「Jira Software」とのシームレスな連携が最大の強みです。インシデントの報告から開発チームへのエスカレーション、原因となったバグの修正までを円滑につなぎ、根本原因の解決を迅速化します。
ITILのフレームワークに準拠した機能も豊富に備えており、インシデント管理だけでなく、問題管理や変更管理にも対応可能です。柔軟なワークフロー設定や、Slack、Microsoft Teamsといった外部ツールとの豊富な連携機能により、自社の運用プロセスに合わせたカスタマイズが容易な点も魅力です。開発部門との連携を重視する企業や、すでにJira製品を利用している企業に最適なツールと言えるでしょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な特徴 | Jira Softwareとの強力な連携、ITIL準拠、柔軟なワークフロー、豊富なアプリ連携 |
| 価格帯 | 小規模チーム向けの無料プランあり。ユーザー数に応じた有料プランが中心。 |
| こんな企業におすすめ | 開発部門との連携を強化したい企業、アジャイル開発とITSMを両立させたい企業 |
ITIL準拠の本格派 ServiceNow
ServiceNowは、ITILに完全に準拠したプロセス管理を実現する、世界的に高いシェアを誇るITSMプラットフォームです。インシデント管理、問題管理、変更管理、構成管理(CMDB)といったITSMの中核プロセスを単一のプラットフォーム上で統合管理できるため、情報が分散せず、IT運用全体の可視性と統制を大幅に向上させます。
AIを活用したインシデントの自動分類や優先度付け、過去の類似インシデントの提示といった高度な機能も搭載しており、オペレーターの業務負荷を軽減し、迅速な解決を支援します。大規模な組織や、厳格なITガバナンスが求められる企業にとって、非常に強力な選択肢となります。IT部門全体の業務プロセスを標準化し、継続的なサービス改善を目指す企業に最適なソリューションです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な特徴 | ITIL完全準拠、単一プラットフォームでの統合管理、AIによる自動化機能、強力なレポーティング機能 |
| 価格帯 | 高機能な分、比較的高価。企業の規模や要件に応じた見積もりが必要。 |
| こんな企業におすすめ | ITILに準拠した厳格なプロセスを構築したい大企業、IT運用全体を統合管理したい企業 |
使いやすい Redmine
Redmineは、オープンソースのプロジェクト管理ツールですが、その柔軟性の高さからインシデント管理(チケット管理)ツールとしても広く活用されています。最大のメリットは、オープンソースであるためライセンス費用が無料であることです。自社サーバーにインストールして利用するため、セキュリティポリシーに応じて柔軟な運用が可能です。
チケットによるインシデントの記録、担当者の割り当て、ステータス管理といった基本的な機能を備えており、直感的でシンプルな操作性が特徴です。また、豊富なプラグインを導入することで、ガントチャートの表示や工数管理など、自社のニーズに合わせて機能を拡張できます。まずはコストを抑えてインシデント管理を始めたい中小企業や、自社でシステムを構築・運用できる技術力のある企業におすすめです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な特徴 | オープンソースで無料、シンプルなチケット管理機能、豊富なプラグインによる高い拡張性 |
| 価格帯 | 無料(サーバー費用や保守・運用コストは別途必要)。 |
| こんな企業におすすめ | コストを抑えてスモールスタートしたい企業、自社で柔軟にカスタマイズしたい企業 |
まとめ
本記事では、インシデント管理の目的と重要性から、具体的な管理フロー、報告書のテンプレート、そして成功のポイントまでを網羅的に解説しました。インシデント管理の最大の目的は、予期せぬITサービスの中断に対し、迅速な復旧作業を行いビジネスへの影響を最小限に抑えることです。この目的を達成することが、顧客満足度と企業への信頼を維持する上で不可欠です。
効果的なインシデント管理を実現するためには、ご紹介した7ステップのフローに沿って対応プロセスを標準化することが結論として重要になります。また、「明確な役割分担」「SLAの設定」「ナレッジベースの活用」という3つのポイントを押さえることで、属人化を防ぎ、組織全体での対応力を強化できます。すぐに使える報告書テンプレートも活用し、記録と情報共有の効率化を図りましょう。
さらに、Jira Service Managementのようなインシデント管理ツールを導入すれば、プロセスの自動化や情報の一元管理が容易になり、さらなる業務効率化が期待できます。この記事を参考に、自社のインシデント管理体制を見直し、安定したサービス提供に向けた第一歩を踏み出してください。
【PR】関連サイト
SHERPA SUITE
〒108-0073東京都港区三田1-2-22 東洋ビル
URL:https://www.sherpasuite.net/